1 考えを持つこと
発表するには、やっぱり自分の考えを持つことが大事です。その考えをまとめるためのツールとして「ワークシート」や「話し合い」があります。
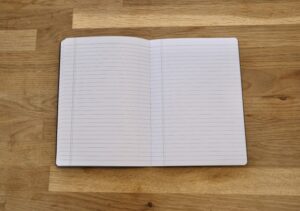
ワークシートというのは、その名の通り、取り組みながら考えをまとめるシートのこと。白紙のノートと違って、あらかじめ考える流れが決められているので、穴埋め形式で整理しやすいんです。中学や高校でよくあった「サブノート」みたいなものですね。
まずは、自分の考えをシートに書き出して、それをもとに話し合いに参加します。自分の考えが全くない状態で話し合いに入るのは、難しいことです。もちろん、友達の話を聞いて「あ、それいいかも!」と気づくこともありますが、最初から何も考えがないと、賛成も反対もできなくなりますよね。
隣の人や小さなグループで話す場があると、自分の意見を言いやすくなります。こうしてまずは練習してみて、その後、みんなの前でも自信を持って発表できるようになるんです。
2 発表の仕方
発表の仕方にも、取り組みやすさに影響するポイントがあります。
例えば、先生と子どもが1対1で向き合って発表するのは、ちょっと緊張しますよね。それよりも、子ども同士で指名し合いながら進めるやり方の方が、気楽に発表しやすいこともあります。
さらに、小さなホワイトボードや実物投影機を使ってノートを映し出すと、発表がスムーズになります。また、名前が書かれた磁石を使って、「この意見に賛成!」と示す方法もアリです。これなら、声を出さなくても発表の一環として参加できます。一番ハードルが低い方法ですね。
子どもたちには、「せっかく授業に参加しているんだから、1回は発表してみようね」と伝えています。いわゆる「爪痕を残す」ってやつです。
発表を促すのには工夫が必要で、自然に任せるだけでは難しいんです。子どもたちが発表しやすい環境を作るのも、教える立場の責任だと思っています。
こんな感じで、「考えを持つこと」と「発表の仕方」についての取り組み、いかがでしょう?子どもたちの成長を見守るお母さんたちにも、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです!
